

◆魔王軍の革新者
「お疲れ様ですレオ、エキドナ様。ではさっそく、今週の投票結果を発表しましょうか」
とある日の夜。魔王城の会議室には、俺とエキドナ、そしてシュティーナの姿があった。
革新的なアイデアを用いて魔王城の設備を改修する、『イノベーション五番勝負』。──先月からやっているエキドナ発案のこの勝負は、なかなかに画期的なものであった。城内の設備が新しくなれば軍団員の福利厚生につながるし、『こんな先進的な設備を導入しています』という情報は対外アピールに広く利用できるからだ。
俺とエキドナ、どちらがより革新的な設備を考案できるか。
そして、どちらがより多くの投票を獲得できるか。
廊下、トイレ、中央広場に会議室──ひと月以上かけて様々な場所でやってきた五番勝負も、ついに今日で最終日なのだった。
「では発表します。五戦目、テーマ『食堂イノベーション』の結果ですが──」
「……」
ごくりとエキドナが喉を鳴らす。しばらくの沈黙の後、気の毒そうにシュティーナが告げた。
「……エキドナ様考案の『爆闘! グルメレース』が171票。レオ考案の『超最先端食券機』が5810票で、レオの勝利です。これでレオの5戦5勝ですね」
「うぇぇぇえ!?」
「まあ、そうなるだろうな」
「そんなバカなッ! 我のプランの方が圧倒的にエキサイティングで、前例がなく、最高に革新的だったはず! なぜこんなにも差がつくのだ……!」
納得いかない、という顔でエキドナがべちべちと机を叩く。そして、俺の方を睨みつけた。
「レオ! 我の案とお前の案、一体どこが違うのだ!? 説明せよ!」
「俺が説明すんのかよ!?」
「お前だ! なぜ我に勝てたのか、勝者としてお前はきっちりと説明する義務がある!」
「わかったよもう……じゃあ逆に聞くが、俺が提案した『超最先端食券機』がどんな内容だったか覚えてるか?」
「無論だとも。あれは実に便利で素晴らしく、先進性のあるアイデアだった」
俺が食堂に試験導入した『超最先端食券機』は、当然ながらただの食券機ではない。食券──ごくごく軽い鉱石で作った、薄い硬券──に《圧縮封印》の呪文がかけてあって、任意の場所で『食券を、料理に』解凍・変換することができるのだ。
変換は不可逆なので、一度料理にしてしまった食券は元に戻せないという問題こそあるが、それ以外は実に好評だった。熱いラーメンを持ち運ぶ時に汁をこぼす心配はないし、地下の食堂から離れた兵舎まで料理をテイクアウトしてもできたてアツアツを食べられる。魔王城でも最近増加しつつあるリモートワークやノマドワークスタイルに対応しつつ、食堂のオペレーション負担も大きく減らす、我ながら実に革新的な案といえるだろう。
この食券、エキドナとシュティーナの二人も大いに活用してくれていたらしく、うんうんと頷いて絶賛している。
「お前の考えたあの食券、なんといっても『料理が冷めない』というのが最高であった! 深夜であろうと早朝であろうと、食券さえ用意しておけばできたてアツアツが食べられるのだからな!」
「私はデザートのアイスを自室で食べられるのが嬉しかったですね。料理を食べ終わった直後はおなかがいっぱいでデザートまで入り切らないことがありましたから……食堂でご飯を食べて、自室に戻って、シャワーを浴びた後ゆっくりアイスを食べられるというのは感動しましたよ」
「あの食券機、外向けに輸出はできるのか? 《圧縮封印》はお前のオリジナル呪文だと聞いているが」
「できるぞ。食券機そのものに『《圧縮封印》を食券にかける』という機構を組み込んであるからな」
食券はそのへんの適当な鉱石を使えばいくらでも調達可能だが、食券機のメンテナンスは魔王城でしかできない。
初回導入コストを控えめにするかわりに、数年かけたメンテナンス費用で元を取る──今回の食券機は『魔王城の食堂改革』でもあり、同時に、長期的な付き合いができる顧客開拓も兼ねたプランだった。
やろうと思えば《圧縮封印》の呪文を他人に伝授することもできるから、仕事の属人化──俺がいないとメンテナンスができない現象──についても問題ない。食券機が世界中に広まった暁には、月々入ってくるライセンス料だけで魔王軍の全員が食っていけるようになるだろう。夢の不労所得というやつだ。
「うーむ、素晴らしい。お前の食券機は本当に素晴らしいアイデア……だと思うのだが……」
「が?」
「……我のグルメレースもお前の食券に負けず劣らず独創的で、前例のないプランだったはず。ここまで差がつくとは、いったい何がいけなかったのだ?」
「そりゃあお前、〝前例がない〟ってだけだもん。あの企画……」
食堂改革のためにエキドナが提案したプラン、『爆闘! グルメレース』は、体重に気を使う女性軍団員向けに考案されたものだった。すなわち、フィットネスと食事の両立だ。
食堂の隣にちょっとした体育館を作り、そこに特設のアスレチックコースを用意する。アスレチックは気力体力魔力すべてを振り絞らないとクリアできないようになっている本格派で、フィットネスに役立つのは間違いない。懐かしい名前を出すなら、機械文明時代の『SASUKE』のようなものだ。
当然SASUKE単体では食事と両立できないため、アスレチックコースの各所に注文した料理が置いてある。走っては食べ、ジャンプしては食べ──それを繰り返してゴールまでたどり着き、最終的なタイムを競うのだ。
このグルメレース、たしかに独創的ではある。
これまでに誰もやらなかった斬新な試み、というところは間違いなかったのだが……。
「どうにも利用者数が伸びませんでしたね。好きな人はそれこそ毎日のようにグルメレースをしていたのですが、大半は物珍しさで一度利用してそれきり、だったようです」
シュティーナがぺらぺらと書類をめくる。書類には食券機とグルメレース、それぞれの利用者数の推移をグラフ化したものが掲載されているのだが、初日から最終日まで常に一定以上の利用者数を誇る食券機と比べ、グルメレースは初日の数字のみが高く、あとは悲しいくらいの低空飛行だった。
「人間界や魔界の歴史は長いからな。〝今日に至るまで誰もやらなかったこと〟っていうのは、たいていが〝これやっぱりダメだわ〟という欠陥を抱えてるものなんだ。理由があってやってないんだよ」
「むう。そういうものか?」
未だ納得いっていない様子のエキドナが、やはり書類をめくり、首をかしげた。
「そういうものだよ。だってお前、〝ご飯を落ち着いて食べられるレストラン〟と〝常に死にそうな状態で料理を食わされるレストラン〟ならどっちがいいよ?」
「そんなの前者に決まっているが!? いくら斬新でも落ち着いて食事できないレストランなど本末転倒だろう!」
「わかってんじゃねえか! お前のグルメレースは後者だよ後者!」
「ううっ……」
エキドナが唸り、がっくしと肩を落とす。
「……お前の言う通り、頭では分かっているのだ。だがいざ企画を考えると、『これじゃあパンチが足りない』『斬新さが足りない』というところばかり気になってしまってな。気がついたらどんどん変な方向に……」
「一人で黙々とアイデア出ししてるとよくあるやつだな、それは……」
今回の五番勝負に限らないが、一人で何かしらのアイデアや企画を考え続けるというのは無謀である。
言ってみれば小さな水筒一本で大砂漠を横断するようなものだ。あっという間に水=アイデアは枯渇するし、暑さで体力は消耗するし、正常な思考能力が奪われて企画はどんどん迷走していく──今回のエキドナのように。
ゆえに、大事なのはリサーチとヒアリングだ。
現在の市場や利用者の声を調査し、何が不足していて何が求められているのかを洗い出す──『革新的』とは程遠い地道な作業だが、どんな斬新なアイデアも結局はこういう小さな一歩から始まるものだ。
実のところ俺の『超最先端食券機』も、メルネスをはじめとする食堂関係者や一般利用者から出た『こういうサービスがあったら嬉しい』という声を多少アレンジしただけである。どんなサービス、どんなコンテンツも、その先に利用者がいるという事実を忘れてはならないという好例だろう。
「……ともあれ、この勝負は全面的にレオの勝利です」
しゅんとしたエキドナの肩に手を置いたシュティーナが、労るような口調で言った。
「五番勝負に勝ったものが《魔王軍の革新者》の称号を手にし、来年の『魔王軍・事業紹介パンフレット』の表紙を飾る。──取り決め通り、称号と表紙はレオのものということでよろしいですか? エキドナ様」
「……そうだな、異論はない」
エキドナが頷いた。その顔にはいつもの笑顔が戻っているが、空元気なのは明らかだ。
「さすがにここまでボロ負けしてはぐうの音も出んというものよ。レオの食券機は魔王城以外での利用も見込めるが、我のアイデアといえば〝前例がない〟だけが取り柄で、どんな事業の役にも立たんしな。ははは……」
「そうか? お前のアイデア、俺は悪くないと思うが」
「同情はよせレオ! 我の出した『爆闘! グルメレース』も、『リリvsエドヴァルト! ガチンコバトルディナーショー!』も、ろくに投票数を稼げなかったではないか!」
「だから一人で結論を出すなってば。……いいか? 一見して大失敗なアイデアも、ちょっとアレンジすればすごくいい素材になったりするんだよ。──《地図投影》!」
指を鳴らし、呪文を発動させる。
とある施設を模したホログラフィを空中に呼び出すと、エキドナとシュティーナは怪訝な顔になり──そして、ぱっと笑顔になった。
「な? 同情なんかじゃなかっただろ」
「エキドナ様、これは……!」
「これならば間違いない……! さっそく企画書の作成に取り掛かるぞ!」
----
……一ヶ月後。
魔王城の近く、まだ雪が残るセシャト山脈の山間に、巨大なテーマパークが完成していた。中央管理室に備わったマイクに向かい、エキドナがノリノリで場内アナウンスを流す。
「良い子の──いや悪い子の諸君、本日は〝エキドナランド〟へようこそ! 魔王と勇者が共同で開発した様々なアトラクションがキミを待っておるぞ! 特におすすめは『爆闘!グルメレース』──身体を思いっきり動かしたいキミにおすすめだッ! 15時からは特設ステージで四天王同士のガチンコバトルショーも開催されるゆえ、ぜひ楽しんでくれ!」
「……よかった。エキドナ様、すっかり元気になりましたね」
声の方を振り向くと、ちょうど仕事を終えたシュティーナが管理室に入ってきたところだった。
このテーマパーク──エキドナ・ランドの管理運営は基本的に軍の一般構成員が行っているが、たまにこうして幹部たちが仕事をすることもある。リリやエドヴァルトならショーへの出演、シュティーナならアトラクションのメンテナンスといった具合だ。仕事が増えて大変なんじゃないかと思ったが、案外いい気分転換になっているらしい。
「あなたは知らないでしょうけど、五番勝負で連敗してた頃のエキドナ様は大変だったんですよ。〝我には企画の才能がない〟とか〝革新的な案なんて一生出せっこない〟とかヘコみまくってて……笑顔になってくれてよかったです」
「あいつは何でもかんでも一人で考えすぎなんだよ。アイデアなんて結局使い方次第だってのに」
このエキドナランドの建設は、実のところもとから決まっていたものである。《商業連合》──大手企業のトップたちが集まった、カネ稼ぎのプロ集団──から魔王軍へ、『魔王城近くの土地を利用してテーマパークを作らないか』という打診が前々から来ていたのだ。
魔王城がそびえるセシャト山脈は天然の要害だ。険しい山々と寒さが人の入植を拒み、山脈中を隅から隅まで探しても、まともな住居は魔王城くらいしか建っていない。管理が大変すぎて、近隣の国もとっくの昔に土地の所有権を放棄している……逆に言うとそれは、フリーの土地が有り余っているということでもある。ドデカいテーマパークを建てるにはうってつけだったのだ。
現地までの移動は《転送門》があるし、巨大なドーム状の結界を張っているから一年を通して快適な気温を提供できる。売上の半分以上を《商業連合》に持っていかれるが、そのかわり建設費用は彼らが持ってくれるし、魔王軍の収入源も増える……といい事づくめである。
土地は問題なし。資金も問題なし。その他もだいたい問題なし。
そんな中で一つだけ難航していたのが『どんなアトラクションを用意するか』だったのだが──エキドナが五番勝負で出したグルメレースや過激なディナーショーが、まさにテーマパークのアトラクションにピッタリだったのだ。
「アトラクションの調子はどうだ?」
「どれも盛況です。特にグルメレースは大人気みたいですよ。アスレチックの途中に設置した『食券』をゲットすると、完走後に食券がそのまま手に入り、好きな時に飲食スペースで食べられる……アスレチックと食事を両立している、まさに勇者と魔王の合体技だと商業連合の方も絶賛してました」
「グルメレースが斬新なアイデアであることは間違いなかったからな。適材適所──どんなアイデアも輝ける場所がある、ってことさ」
エキドナの方を見ると、未だに楽しそうに場内アナウンスをやっている。
あの五番勝負、勝敗だけを見れば俺の勝ちだったのは間違いないだろう。エキドナの没アイデアをテーマパークに流用すると言い出したのも俺だし、《魔王軍の革新者》の二つ名が俺のものになったのは、まあ妥当な結末に見える。
──しかし、本当にそうだろうか?
俺が思うに、真のイノベーターとは『新しい場所、新しい分野に向けて大勢を引っ張っていける人』だ。
そもそもの話をすれば、『福利厚生と対外アピール強化のため、イノベーション五番勝負をやろう!』と言い出したのはエキドナだし、そのための予算を確保したのもエキドナだ。言い出しっぺのあいつがいなければ俺の『食券』が世に出ることもなかったし、アトラクションの案が出ることもなかったし、テーマパークの建設も大いに遅れていただろう。
「……さてさて。本当に《魔王軍の革新者》の称号を手にするべきは、俺とお前のどっちなんだろうな?」
「なんだレオ!? 何か言ったか!?」
「なんでもないよ!」
怪訝そうにこちらを見やるエキドナに手を振り、俺は笑顔でそう返した。
とある日の夜。魔王城の会議室には、俺とエキドナ、そしてシュティーナの姿があった。
革新的なアイデアを用いて魔王城の設備を改修する、『イノベーション五番勝負』。──先月からやっているエキドナ発案のこの勝負は、なかなかに画期的なものであった。城内の設備が新しくなれば軍団員の福利厚生につながるし、『こんな先進的な設備を導入しています』という情報は対外アピールに広く利用できるからだ。
俺とエキドナ、どちらがより革新的な設備を考案できるか。
そして、どちらがより多くの投票を獲得できるか。
廊下、トイレ、中央広場に会議室──ひと月以上かけて様々な場所でやってきた五番勝負も、ついに今日で最終日なのだった。
「では発表します。五戦目、テーマ『食堂イノベーション』の結果ですが──」
「……」
ごくりとエキドナが喉を鳴らす。しばらくの沈黙の後、気の毒そうにシュティーナが告げた。
「……エキドナ様考案の『爆闘! グルメレース』が171票。レオ考案の『超最先端食券機』が5810票で、レオの勝利です。これでレオの5戦5勝ですね」
「うぇぇぇえ!?」
「まあ、そうなるだろうな」
「そんなバカなッ! 我のプランの方が圧倒的にエキサイティングで、前例がなく、最高に革新的だったはず! なぜこんなにも差がつくのだ……!」
納得いかない、という顔でエキドナがべちべちと机を叩く。そして、俺の方を睨みつけた。
「レオ! 我の案とお前の案、一体どこが違うのだ!? 説明せよ!」
「俺が説明すんのかよ!?」
「お前だ! なぜ我に勝てたのか、勝者としてお前はきっちりと説明する義務がある!」
「わかったよもう……じゃあ逆に聞くが、俺が提案した『超最先端食券機』がどんな内容だったか覚えてるか?」
「無論だとも。あれは実に便利で素晴らしく、先進性のあるアイデアだった」
俺が食堂に試験導入した『超最先端食券機』は、当然ながらただの食券機ではない。食券──ごくごく軽い鉱石で作った、薄い硬券──に《圧縮封印》の呪文がかけてあって、任意の場所で『食券を、料理に』解凍・変換することができるのだ。
変換は不可逆なので、一度料理にしてしまった食券は元に戻せないという問題こそあるが、それ以外は実に好評だった。熱いラーメンを持ち運ぶ時に汁をこぼす心配はないし、地下の食堂から離れた兵舎まで料理をテイクアウトしてもできたてアツアツを食べられる。魔王城でも最近増加しつつあるリモートワークやノマドワークスタイルに対応しつつ、食堂のオペレーション負担も大きく減らす、我ながら実に革新的な案といえるだろう。
この食券、エキドナとシュティーナの二人も大いに活用してくれていたらしく、うんうんと頷いて絶賛している。
「お前の考えたあの食券、なんといっても『料理が冷めない』というのが最高であった! 深夜であろうと早朝であろうと、食券さえ用意しておけばできたてアツアツが食べられるのだからな!」
「私はデザートのアイスを自室で食べられるのが嬉しかったですね。料理を食べ終わった直後はおなかがいっぱいでデザートまで入り切らないことがありましたから……食堂でご飯を食べて、自室に戻って、シャワーを浴びた後ゆっくりアイスを食べられるというのは感動しましたよ」
「あの食券機、外向けに輸出はできるのか? 《圧縮封印》はお前のオリジナル呪文だと聞いているが」
「できるぞ。食券機そのものに『《圧縮封印》を食券にかける』という機構を組み込んであるからな」
食券はそのへんの適当な鉱石を使えばいくらでも調達可能だが、食券機のメンテナンスは魔王城でしかできない。
初回導入コストを控えめにするかわりに、数年かけたメンテナンス費用で元を取る──今回の食券機は『魔王城の食堂改革』でもあり、同時に、長期的な付き合いができる顧客開拓も兼ねたプランだった。
やろうと思えば《圧縮封印》の呪文を他人に伝授することもできるから、仕事の属人化──俺がいないとメンテナンスができない現象──についても問題ない。食券機が世界中に広まった暁には、月々入ってくるライセンス料だけで魔王軍の全員が食っていけるようになるだろう。夢の不労所得というやつだ。
「うーむ、素晴らしい。お前の食券機は本当に素晴らしいアイデア……だと思うのだが……」
「が?」
「……我のグルメレースもお前の食券に負けず劣らず独創的で、前例のないプランだったはず。ここまで差がつくとは、いったい何がいけなかったのだ?」
「そりゃあお前、〝前例がない〟ってだけだもん。あの企画……」
食堂改革のためにエキドナが提案したプラン、『爆闘! グルメレース』は、体重に気を使う女性軍団員向けに考案されたものだった。すなわち、フィットネスと食事の両立だ。
食堂の隣にちょっとした体育館を作り、そこに特設のアスレチックコースを用意する。アスレチックは気力体力魔力すべてを振り絞らないとクリアできないようになっている本格派で、フィットネスに役立つのは間違いない。懐かしい名前を出すなら、機械文明時代の『SASUKE』のようなものだ。
当然SASUKE単体では食事と両立できないため、アスレチックコースの各所に注文した料理が置いてある。走っては食べ、ジャンプしては食べ──それを繰り返してゴールまでたどり着き、最終的なタイムを競うのだ。
このグルメレース、たしかに独創的ではある。
これまでに誰もやらなかった斬新な試み、というところは間違いなかったのだが……。
「どうにも利用者数が伸びませんでしたね。好きな人はそれこそ毎日のようにグルメレースをしていたのですが、大半は物珍しさで一度利用してそれきり、だったようです」
シュティーナがぺらぺらと書類をめくる。書類には食券機とグルメレース、それぞれの利用者数の推移をグラフ化したものが掲載されているのだが、初日から最終日まで常に一定以上の利用者数を誇る食券機と比べ、グルメレースは初日の数字のみが高く、あとは悲しいくらいの低空飛行だった。
「人間界や魔界の歴史は長いからな。〝今日に至るまで誰もやらなかったこと〟っていうのは、たいていが〝これやっぱりダメだわ〟という欠陥を抱えてるものなんだ。理由があってやってないんだよ」
「むう。そういうものか?」
未だ納得いっていない様子のエキドナが、やはり書類をめくり、首をかしげた。
「そういうものだよ。だってお前、〝ご飯を落ち着いて食べられるレストラン〟と〝常に死にそうな状態で料理を食わされるレストラン〟ならどっちがいいよ?」
「そんなの前者に決まっているが!? いくら斬新でも落ち着いて食事できないレストランなど本末転倒だろう!」
「わかってんじゃねえか! お前のグルメレースは後者だよ後者!」
「ううっ……」
エキドナが唸り、がっくしと肩を落とす。
「……お前の言う通り、頭では分かっているのだ。だがいざ企画を考えると、『これじゃあパンチが足りない』『斬新さが足りない』というところばかり気になってしまってな。気がついたらどんどん変な方向に……」
「一人で黙々とアイデア出ししてるとよくあるやつだな、それは……」
今回の五番勝負に限らないが、一人で何かしらのアイデアや企画を考え続けるというのは無謀である。
言ってみれば小さな水筒一本で大砂漠を横断するようなものだ。あっという間に水=アイデアは枯渇するし、暑さで体力は消耗するし、正常な思考能力が奪われて企画はどんどん迷走していく──今回のエキドナのように。
ゆえに、大事なのはリサーチとヒアリングだ。
現在の市場や利用者の声を調査し、何が不足していて何が求められているのかを洗い出す──『革新的』とは程遠い地道な作業だが、どんな斬新なアイデアも結局はこういう小さな一歩から始まるものだ。
実のところ俺の『超最先端食券機』も、メルネスをはじめとする食堂関係者や一般利用者から出た『こういうサービスがあったら嬉しい』という声を多少アレンジしただけである。どんなサービス、どんなコンテンツも、その先に利用者がいるという事実を忘れてはならないという好例だろう。
「……ともあれ、この勝負は全面的にレオの勝利です」
しゅんとしたエキドナの肩に手を置いたシュティーナが、労るような口調で言った。
「五番勝負に勝ったものが《魔王軍の革新者》の称号を手にし、来年の『魔王軍・事業紹介パンフレット』の表紙を飾る。──取り決め通り、称号と表紙はレオのものということでよろしいですか? エキドナ様」
「……そうだな、異論はない」
エキドナが頷いた。その顔にはいつもの笑顔が戻っているが、空元気なのは明らかだ。
「さすがにここまでボロ負けしてはぐうの音も出んというものよ。レオの食券機は魔王城以外での利用も見込めるが、我のアイデアといえば〝前例がない〟だけが取り柄で、どんな事業の役にも立たんしな。ははは……」
「そうか? お前のアイデア、俺は悪くないと思うが」
「同情はよせレオ! 我の出した『爆闘! グルメレース』も、『リリvsエドヴァルト! ガチンコバトルディナーショー!』も、ろくに投票数を稼げなかったではないか!」
「だから一人で結論を出すなってば。……いいか? 一見して大失敗なアイデアも、ちょっとアレンジすればすごくいい素材になったりするんだよ。──《地図投影》!」
指を鳴らし、呪文を発動させる。
とある施設を模したホログラフィを空中に呼び出すと、エキドナとシュティーナは怪訝な顔になり──そして、ぱっと笑顔になった。
「な? 同情なんかじゃなかっただろ」
「エキドナ様、これは……!」
「これならば間違いない……! さっそく企画書の作成に取り掛かるぞ!」
----
……一ヶ月後。
魔王城の近く、まだ雪が残るセシャト山脈の山間に、巨大なテーマパークが完成していた。中央管理室に備わったマイクに向かい、エキドナがノリノリで場内アナウンスを流す。
「良い子の──いや悪い子の諸君、本日は〝エキドナランド〟へようこそ! 魔王と勇者が共同で開発した様々なアトラクションがキミを待っておるぞ! 特におすすめは『爆闘!グルメレース』──身体を思いっきり動かしたいキミにおすすめだッ! 15時からは特設ステージで四天王同士のガチンコバトルショーも開催されるゆえ、ぜひ楽しんでくれ!」
「……よかった。エキドナ様、すっかり元気になりましたね」
声の方を振り向くと、ちょうど仕事を終えたシュティーナが管理室に入ってきたところだった。
このテーマパーク──エキドナ・ランドの管理運営は基本的に軍の一般構成員が行っているが、たまにこうして幹部たちが仕事をすることもある。リリやエドヴァルトならショーへの出演、シュティーナならアトラクションのメンテナンスといった具合だ。仕事が増えて大変なんじゃないかと思ったが、案外いい気分転換になっているらしい。
「あなたは知らないでしょうけど、五番勝負で連敗してた頃のエキドナ様は大変だったんですよ。〝我には企画の才能がない〟とか〝革新的な案なんて一生出せっこない〟とかヘコみまくってて……笑顔になってくれてよかったです」
「あいつは何でもかんでも一人で考えすぎなんだよ。アイデアなんて結局使い方次第だってのに」
このエキドナランドの建設は、実のところもとから決まっていたものである。《商業連合》──大手企業のトップたちが集まった、カネ稼ぎのプロ集団──から魔王軍へ、『魔王城近くの土地を利用してテーマパークを作らないか』という打診が前々から来ていたのだ。
魔王城がそびえるセシャト山脈は天然の要害だ。険しい山々と寒さが人の入植を拒み、山脈中を隅から隅まで探しても、まともな住居は魔王城くらいしか建っていない。管理が大変すぎて、近隣の国もとっくの昔に土地の所有権を放棄している……逆に言うとそれは、フリーの土地が有り余っているということでもある。ドデカいテーマパークを建てるにはうってつけだったのだ。
現地までの移動は《転送門》があるし、巨大なドーム状の結界を張っているから一年を通して快適な気温を提供できる。売上の半分以上を《商業連合》に持っていかれるが、そのかわり建設費用は彼らが持ってくれるし、魔王軍の収入源も増える……といい事づくめである。
土地は問題なし。資金も問題なし。その他もだいたい問題なし。
そんな中で一つだけ難航していたのが『どんなアトラクションを用意するか』だったのだが──エキドナが五番勝負で出したグルメレースや過激なディナーショーが、まさにテーマパークのアトラクションにピッタリだったのだ。
「アトラクションの調子はどうだ?」
「どれも盛況です。特にグルメレースは大人気みたいですよ。アスレチックの途中に設置した『食券』をゲットすると、完走後に食券がそのまま手に入り、好きな時に飲食スペースで食べられる……アスレチックと食事を両立している、まさに勇者と魔王の合体技だと商業連合の方も絶賛してました」
「グルメレースが斬新なアイデアであることは間違いなかったからな。適材適所──どんなアイデアも輝ける場所がある、ってことさ」
エキドナの方を見ると、未だに楽しそうに場内アナウンスをやっている。
あの五番勝負、勝敗だけを見れば俺の勝ちだったのは間違いないだろう。エキドナの没アイデアをテーマパークに流用すると言い出したのも俺だし、《魔王軍の革新者》の二つ名が俺のものになったのは、まあ妥当な結末に見える。
──しかし、本当にそうだろうか?
俺が思うに、真のイノベーターとは『新しい場所、新しい分野に向けて大勢を引っ張っていける人』だ。
そもそもの話をすれば、『福利厚生と対外アピール強化のため、イノベーション五番勝負をやろう!』と言い出したのはエキドナだし、そのための予算を確保したのもエキドナだ。言い出しっぺのあいつがいなければ俺の『食券』が世に出ることもなかったし、アトラクションの案が出ることもなかったし、テーマパークの建設も大いに遅れていただろう。
「……さてさて。本当に《魔王軍の革新者》の称号を手にするべきは、俺とお前のどっちなんだろうな?」
「なんだレオ!? 何か言ったか!?」
「なんでもないよ!」
怪訝そうにこちらを見やるエキドナに手を振り、俺は笑顔でそう返した。
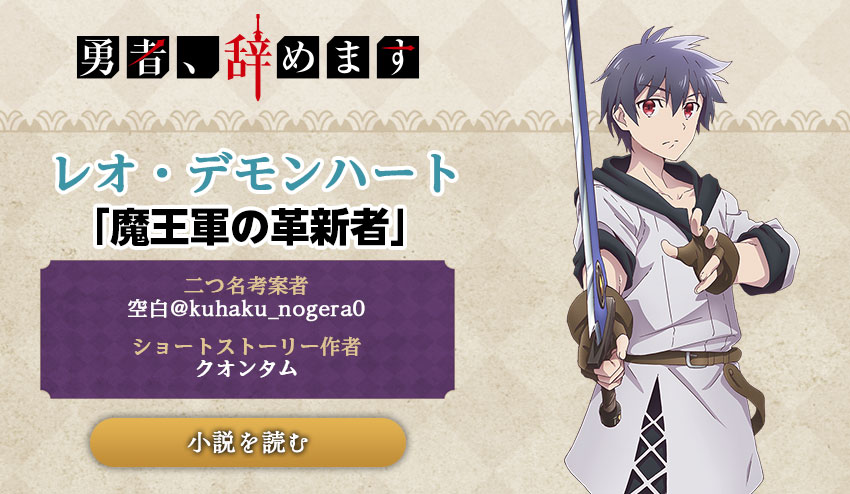



- S
- M
- L
- 画面拡大
- 画面縮小

